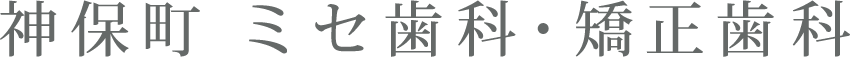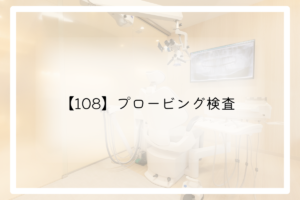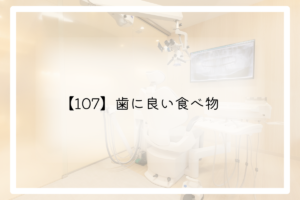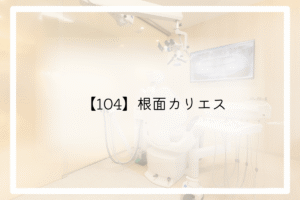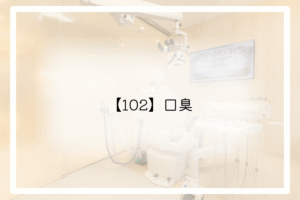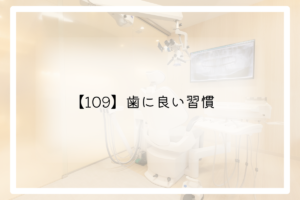
こんにちは、衛生士の會澤です。
今回は歯に良い習慣についてお話しします。
まず食生活に関してです。
①よく噛んで食べる
噛む時は前歯で噛み切み、奥歯に送り込みすり潰すのが正しい咀嚼の流れです。よく噛むことによって唾液の分泌を促し、口内を中和して虫歯菌の繁殖を抑えることができます。回数は1口30回を目安によく噛んでください。
②飲料水
スポーツドリンクには多くの糖質が含まれます。
なので、水代わりに飲んだり就寝前に飲むと、口内に糖質が残り続けて歯垢の増殖を助けてしまい虫歯を引き起こす要因となるので注意しましょう。
pHの低い飲み物はエナメル質が溶ける可能性があります。例えばコーラ、レモンハイ、ビタミンCドリンク、スポーツドリンク、野菜ジュース、オレンジジュース、ビールです。
逆にpHの高い飲み物は、水、牛乳、麦茶です。
なので、飲み物を飲む時は水、牛乳、麦茶などにしましょう。
細菌は糖質から酸を産生する為、お口の中のpHも酸性に傾きます。食事後、唾液の働きで糖質は洗い流され、酸の中和が進みpHは中性に戻ります。これが食事の度に繰り返されるのです。飲み物にも注意する必要があります。
③お口の中のセルフケア
お口の中は数億個レベルで細菌がいるため毎日しっかり朝・昼・晩と歯を磨きましょう。昼食後磨くのが難しい場合は朝・夜だけは必ず磨いてください。
その際に歯ブラシだけではなくフロスや糸ようじ、歯間ブラシをしっかり使うのが必須ですが、もし出先で難しい場合は1日1回夜だけはしっかり時間を取り行いましょう。
またプラスアルファーで、マウスウォッシュやウォーターピックを使うのも良いでしょう。
今回は歯に良い習慣についてお話しさせていただきました。
少しでも参考になれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
神保町ミセ歯科•矯正歯科
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目4 神保町1-4ビル 2F
東京メトロ半蔵門線神保町駅A5出口 徒歩1分
都営地下鉄三田線A5出口 徒歩1分
都営地下鉄新宿線A5出口 徒歩1分
【ネット予約可・公式】神保町の歯医者|神保町ミセ歯科・矯正歯科